薬師 洋行 Hiroyuki Yakushi
富山県出身。1969年にアルペンスキー・ワールドカップを初めて取材した後、オリンピック、世界選手権など世界トップクラスの競技会でアルペンスキーの撮影を続ける。1972年の札幌オリンピックで組織委員会公式カメラマンを務めた後、2014年ソチまで12回の冬季オリンピックを取材。1993年に雫石で開催された世界選手権では組織委員会報道委員を務めた。自転車のツール・ド・フランス、全英オープンゴルフ、テニスのウィンブルドン選手権など、スキー以外の取材も多い。
インタビュー:2014年12月5日

薬師 洋行 Hiroyuki Yakushi
富山県出身。1969年にアルペンスキー・ワールドカップを初めて取材した後、オリンピック、世界選手権など世界トップクラスの競技会でアルペンスキーの撮影を続ける。1972年の札幌オリンピックで組織委員会公式カメラマンを務めた後、2014年ソチまで12回の冬季オリンピックを取材。1993年に雫石で開催された世界選手権では組織委員会報道委員を務めた。自転車のツール・ド・フランス、全英オープンゴルフ、テニスのウィンブルドン選手権など、スキー以外の取材も多い。

モデル
河野 克幸 Katsuyuki Kono
1981年生まれ、野沢温泉村出身。中学卒業後オーストリアへ渡り、アルペンスキーで欧州を転戦。2003年からスキークロスでワールドカップを転戦。TVドラマでスキーシーンのスタントを担当、自身で映像制作も。スキー、スノボのレンタルショップを経営。現在、野沢温泉スキークラブでジュニアのコーチ。

モデル
河野 健児 Kenji Kono
1983年生まれ、野沢温泉村出身。幼い頃からアルペンスキー選手として活動、2002年からスキークロスの選手としてワールドカップを転戦、入賞5回。TVドラマでスキーシーンのスタントを担当。野沢温泉村で自然体験施設「Nozawa Green Field」を運営。現在、野沢温泉スキークラブでジュニアのコーチ。

写真家の薬師 洋行さんは、45年間にわたってアルペンスキーのワールドカップ、冬季オリンピック、世界選手権などを撮り続け、アルペンスキーの魅力を伝えてきました。その薬師さんが、久しぶりに故郷の立山(富山県)に戻り、トップクラスのスキーヤー、スノーボーダーを撮影しました。その撮影を中心に、アルペンスキーの魅力についてお聞きしました。
編集委員
薬師先生は、ワールドカップの黎明期から、半世紀近くアルペンスキーを撮り続けていらっしゃるわけですが、これだけの長い間、情熱を持ち続けられる理由は何ですか。
薬師
それは、アルペンスキーという競技とそこにいる選手の魅力、それに尽きるのではないかと思います。ワールドカップは世界のトップを目指す人が集まってくる競技会で、スキーのテクニックはもちろん、大会を取り巻く環境なども知れば知るほど面白い。スキー、ブーツ、ウエアなどの道具を取ってみても、風洞実験などを繰り返しながら限界に挑戦している。作る人も滑る人もみんながギリギリのところで勝負している、という面白さがあります。
スピードも昔とは桁違いに速くなっていて、たとえば僕が最初にワールドカップに行ったときは優勝者が3分10秒くらいで滑っていたコースを、いまは2分30秒くらいで滑ってくる。身体を使うスポーツで、時速100キロを超えるのは、ほかにないんじゃないですか。そこで戦っている選手のキャラクターも様々で、寡黙な人がいれば、大騒ぎする陽気な選手もいる。そういった魅力が、僕の中からは離れていかなかったということですね。

編集委員
今回はそんな競技の世界とは離れて、立山で2人のスキーヤーと向き合っての撮影となりました。ワールドカップのアルペンスキーやスキークロスでご活躍された河野 克幸さん、健児さんご兄弟を撮影されたわけですが、自然の美しさとスキーヤーの格好良さがとても印象的です。こうした撮影は、前から温めていたものですか。
薬師
もともと、2人の親父さんと45年近くの付き合いがあるんですよ。つまり、彼らが生まれる前からですね。兄弟は、2人ともワールドカップのアルペンスキーやスキークロスで戦ってきたのですが、以前から「選手を辞めたら一度写真を撮ろうよ」という話をしていたのです。昨年、弟の健児が現役を引退して、ようやく撮影することができました。
編集委員
競技以外の写真を撮るのは珍しいのでは?
薬師
本当は競技も今回のような写真も両方撮りたいんだけど、ワールドカップをメインに撮っていると、こういうのはなかなか撮れないんですよ。もう30年くらい撮れなかったんじゃないかな。今回は、とてもいいチャンスでした。
編集委員
撮影場所として立山を選んだのはなぜですか。
薬師
スキーカメラマンの仲間内では、立山は“聖地”のようなところです。広い範囲内にいろんな斜面があって、時間の変化とともに様々な写真を撮影できます。雪も多く、11月は新雪、4月半ば以降も新雪、残雪を含めて7月頃まで撮影できます。跡一つない、白いキャンバスに、スキーヤーはいかにきれいなシュプールを付けるか、撮る側はいかに一筆書きの絵を描かせるか、というスキー写真の楽しみを実現するのに絶好の場所です。

編集委員
1日の撮影について教えてください。撮影はどのような手順で行いますか?
薬師
山小屋に泊まって、晴れれば朝からの撮影になります。撮影場所に行って、滑る場所が決まると、スキーヤーにはスタートするポイントに上がってもらいます。そして、滑ってくると、場所を変えてまた上がってもらって、の繰り返しです。
滑るコースは、基本的にスキーヤーのインスピレーションに任せています。でも、滑る斜面と岩などの邪魔なものは、お互いに見れば分かる。そうすると、スキーヤーが実際に滑るコースは、こちらの考えとほぼ一致するんですよ。ただ、(写真を指しながら)このようなジャンプの写真は、「ここからこんなふうに飛んで」という注文を付けることはあります。
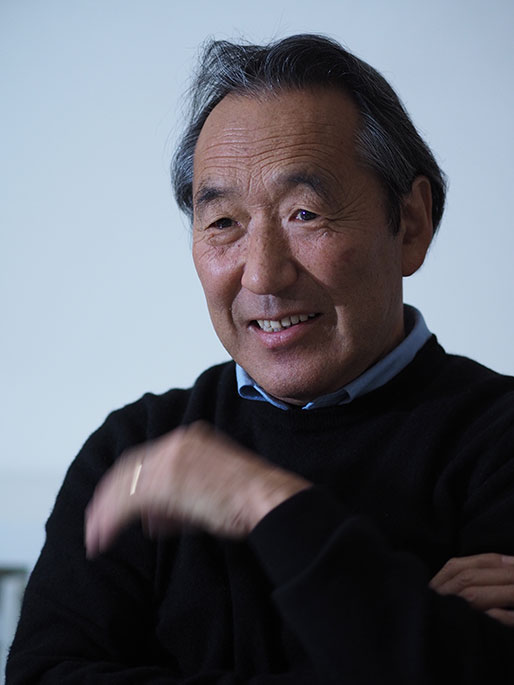
編集委員
撮影で特に大切なことは何ですか。
薬師
何を写したいのかをしっかりイメージして撮影を始めることが大事ですね。景色が美しいから、このカットは景色を主体にしてスキーヤーは点景で入れようとか、スキーヤーがうまいから滑りを主体に撮ろうとか。それをはっきり分けて撮らないと、中途半端なものになりかねない。(別の写真を指しながら)たとえばこの写真で山を入れて撮ると、スキーヤーはもう点でしかないわけですね。すると、スキーヤーが上げる雪煙の良さは半減するじゃないですか。
スキーヤー主体で狙う場合、専門的にはストックワークの形とかスキーの向いている角度とかも見ますけれど、いい絵かどうか分ける大きな要素は、光と陰と雪煙ですね。光の状態を見て、雪煙がどういう形になるか、逆光気味であればそれがどんなシルエットになるか、そういったものが長年の経験でお互いに分かるようになっているのが理想ですね。どこを滑ってくるかも大切です。たとえいい雪煙が上がっても、完全な日陰で滑っていてはいい写真にはなりませんから。
編集委員
そうすると、1回の滑りで撮るべきポイントは、本当に限られてくるのではないですか。
薬師
そうですね。滑り初めから、ずっとカメラで追っかけますけれど、いいポイントは一滑りに1カ所あればいいくらい。だから、本当に一滑りで1カットか2カット、セレクトできればいいほうですね。彼らは若くて体力があるから、何度も上に上がって滑ってくれたけど、それでも1日に滑ったのは、2人合わせて、20から25本でしょう。だから、1本1本を大切に撮影しないと、お互いに大変なんです。

編集委員
久しぶりの立山は、充実感も高かったのではないですか?
薬師
結構、満足できるものが撮れたかな、という思いはあります。ただ、課題も見つかりました。1つは、スキー環境の変化。最近はこういうところで滑る人が多くなって、すぐに跡が付くんですよ。跡が付いた斜面は撮影には使えないので、自分たちも1回ごとに場所を変えて撮影するのですが、撮りたいところを横切る人もいたりして難しいですね。
もう1つは、装備の問題。写真を見るとお分かりのように、スキーヤーがリュックを背負っているでしょう。なぜリュックを背負っているかというと、スタート地点に上るときに、スノーシューを履いたり、スキーシール[※]を使うからですね。それを置いてくるわけにもいかないから、リュックに入れて滑ってくる。スノーシューやスキーシールのおかげで滑る回数を増やせるし、これがいまのスタイルだからいいと言えばいいんだけど…。
でも、僕は古い世代だから、かっこいいスキーヤーの形として、スキーズボンにニットのセーターに、ゴーグルにニットの帽子。そんな姿が頭の中にあるわけですよ(笑い)。これを解決するには、もう1人、荷物持ちが必要だなとか、そんなことを考えています。今度は、リュックを背負わなくていい状態を作り出してスキーヤーを撮ってみたいですね。
※ スキーシール:登行時にスキー板の底面に貼り付けて使う道具。後方に滑らないようにする毛羽だったテープ状の物で、元々はアザラシの毛皮でできていた。現在はナイロンなどの合成樹脂による製品が主流になっている。

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi

Copyright © Hiroyuki Yakushi